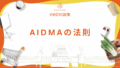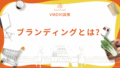「お店のディスプレイ、きれいにしているのに売上に繋がらない…」
「VMDってよく聞くけど、ディスプレイと何が違うの?」
店舗運営においてよく使われる「ディスプレイ」と「VMD」。この2つの言葉の意味を正しく理解することは、売れる店づくりの第一歩です。
結論から言うと、両者の違いは「戦術」と「戦略」の違いです。
- ディスプレイ = 商品を魅力的に見せるための「点」の戦術
- VMD = お客様を惹きつけ、購買に導くための「店全体」の戦略
この記事では、この決定的な違いを、具体的な手法と共に分かりやすく解説します。
料理でたとえる!「ディスプレイ」と「VMD」の決定的違い
この2つの関係性を、レストランの料理にたとえてみましょう。
「ディスプレイ」は、完成した料理の美しい「盛り付け」です。
美味しそうに見せるための、いわば最後の仕上げ。どれだけ美しい盛り付けでも、料理そのもの(商品)や、お店の雰囲気(レイアウト)と合っていなければ、お客様の満足には繋がりません。
一方、「VMD」は、お客様を満足させるための「コース料理全体のレシピと提供計画」です。
前菜(入店)からメインディッシュ(主력商品)、デザート(レジ前のついで買い)まで、お客様がどうすれば最も食事を楽しんでくれるかを考え、最高の体験を設計する。これがVMDの考え方です。美しい「盛り付け(ディスプレイ)」も、この大きな戦略の一部なのです。
「点」を飾る技術、ディスプレイ
ディスプレイとは、特定の場所(Point)で、商品を魅力的に見せるための装飾や陳列の技術そのものを指します。
ショーウィンドウや、店内のテーブルの上、棚の一角など、限られたスペースで世界観を表現し、お客様の視線を集めることが主な目的です。これはVMDという大きな戦略を構成する、重要な「戦術」の一つです。
「店全体」を設計する戦略、VMD
VMD(ビジュアル・マーチャンダイジング)とは、お客様の購買意欲を視覚的に高め、売上を最大化するための店づくり全体の戦略です。
お客様がお店を認知し、入店し、店内を回遊し、商品を選び、購入するまでの一連の流れをトータルで設計します。その戦略を実行するために、VMDには大きく分けて3つの要素があります。
① VP (ビジュアル・プレゼンテーション)|お客様を「入店」に導く、店の顔
VPは、店の前を通るお客様の足を止め、入店を促すための最も重要な仕掛けです。主にショーウィンドウや入口付近のディスプレイがこれにあたります。お店のコンセプトや旬のテーマを表現し、「なんだか面白そうなお店だな」と思わせることが目的です。
② PP (ポイント・オブ・セールス・プレゼンテーション)|お客様の足を「止める」、店内の主役
PPは、入店したお客様を特定の売場へ誘導し、足を止めさせるためのディスプレイです。通路に面した棚の端(エンド)や、壁面のディスプレイなどがこれにあたります。そのお店の「今、一番見てほしい商品」を主役に、テーマ性のある陳列で商品をアピールします。
③ IP (アイテム・プレゼンテーション)|お客様が「手に取る」、商品の陳列
IPは、お客様が実際に商品を比較検討し、手に取る場所の陳列です。つまり、日常的な商品棚そのものを指します。ここでは、商品の分類を分かりやすくしたり、フェイスを整えたり、POPで特徴を補足したりして、お客様が選びやすく、買いやすい状態を作ることが目的です。
まとめ:「ディスプレイ」を磨き、「VMD」で売上を最大化する
「ディスプレイ」と「VMD」の違いをおさらいしましょう。
- ディスプレイは、商品を魅力的に見せる「点」の技術。
- VMDは、VP・PP・IPを連動させ、お客様を購買へと導く「店全体」の戦略。
美しいディスプレイ(点)を作ることはもちろん重要です。しかし、それらが連動し、お客様をスムーズに誘導するVMD(戦略)の視点がなければ、売上アップには繋がりません。
ぜひ、個々の「盛り付け」を磨くと同時に、お客様を最高にもてなす「コース料理の全体設計」という視点で、あなたのお店を見直してみてはいかがでしょうか。